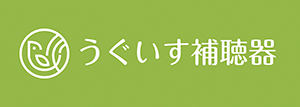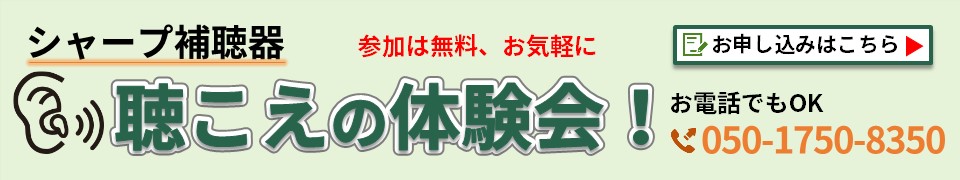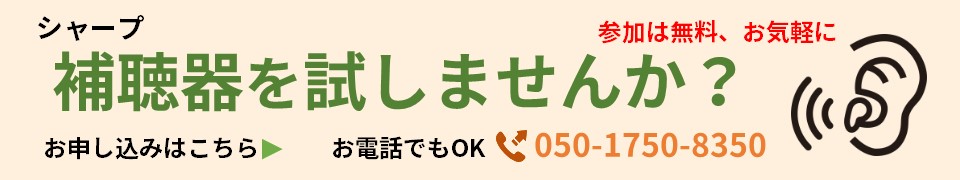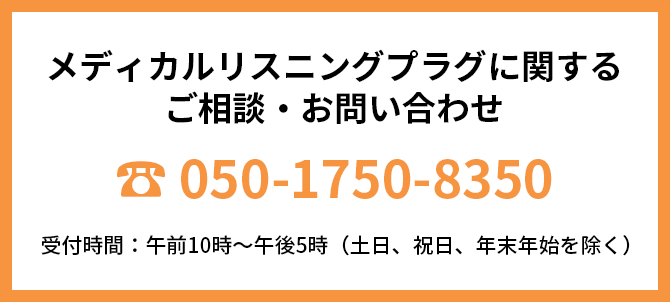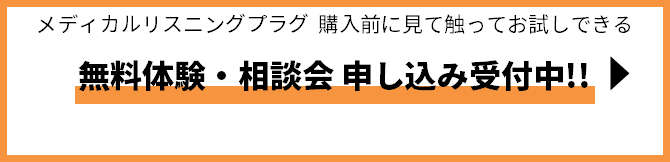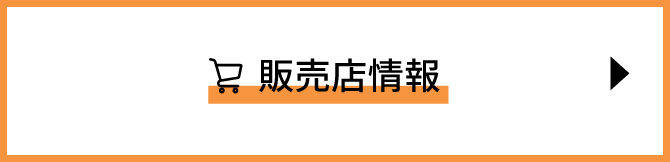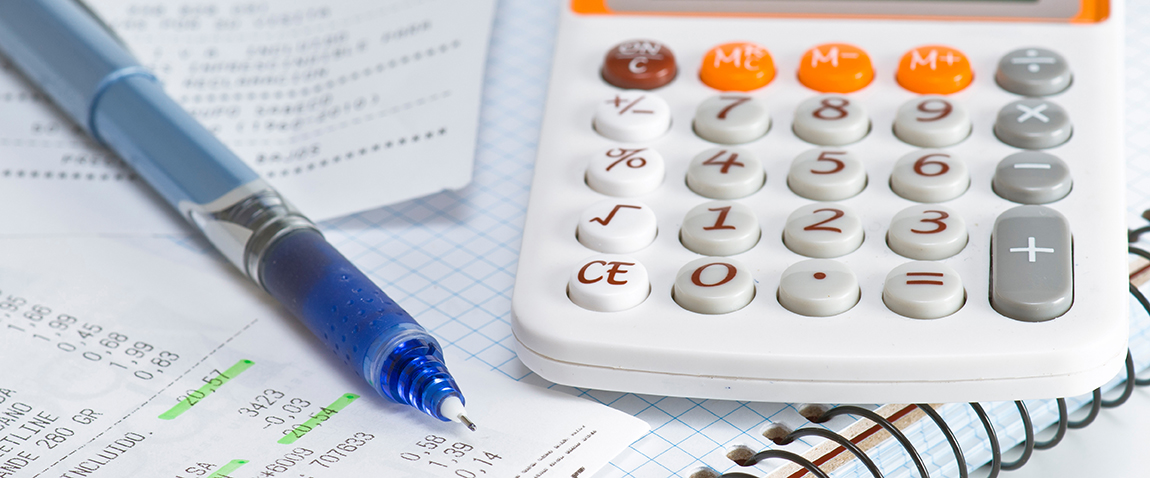
補聴器購入は医療費控除の対象?年金受給者もOK?要件や申請方法を解説!
2024.06.19
「最近聞こえにくいと感じるようになった・・・」そんな人の中には、補聴器の購入を検討している人も多いのではないでしょうか。補聴器は、国の認める医療機器のひとつ。でも、少し値段が高めに感じる、ということで、補聴器購入を躊躇されている方も少なからずいらっしゃるように思います。
今回は、そんな補聴器購入において、医療費控除が受けられるのかどうかや、申請する際のポイントなどについて解説します。
目次
補聴器の購入で医療費控除は受けられる?
結論から言うと、所定の手順にしたがって購入することで、補聴器購入金額について医療費控除を受けることは可能です。(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)
医療費控除とは、本人や扶養家族のために支払った医療費が、国の定める一定金額を超えた場合に利用できる所得控除のひとつです。
これまで補聴器の購入代金は、医療費控除の対象になるかについて全国統一の基準がなく、各税務署の判断とされていましたが、平成30年度(2018年度)から、補聴器の購入金額も医療費控除の対象となりました。
医療費控除を受けられる人はどんな人?高齢者や年金受給者も受けられる?補聴器の電池代や修理費用も対象?
補聴器購入において医療費控除を受けることができるのは、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の認定する「補聴器相談医」から、補聴器の必要性が認められた人です。
高齢者や年金受給中の人でも、確定申告をすれば補聴器の購入費用で医療費控除を受けることが可能です。
ただし、そもそも医療費控除とは「所得税や住民税の控除が受けられる制度」ですので、すでに所得税や住民税が非課税だという人は、控除する対象がないため医療費控除は受けられません。
また、医療費控除の対象となるのは「補聴器本体の購入費のみ」で、補聴器の電池代や修理にかかる費用などは、基本的には医療費控除の対象とはなりませんので注意が必要です。
補聴器購入で医療費控除を受ける手順

実際に補聴器購入費で医療費控除を受ける場合の、踏むべき手順を解説します。手順通りに購入を進めなければ控除が受けられない場合もあるので、しっかりチェックしておいてくださいね。
①補聴器相談医を受診する
補聴器の購入を検討し始めたら、まずは「補聴器相談医」を受診しましょう。補聴器相談医とは、専門のカリキュラムを履修した耳鼻咽喉科医のことで、いわば「難聴や補聴器のスペシャリスト」です。
補聴器相談医は全国の医療機関に在籍しているので、ぜひ近くの補聴器相談医を探して受診してみてくださいね。
お近くの補聴器相談医を探す:補聴器相談医名簿
診察を受けて補聴器が必要であると診断された場合、補聴器相談医に「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」という書類を作成してもらいましょう。
②補聴器相談医からの書類を持参して補聴器販売店に行く
補聴器相談医が作成した「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を持参して、補聴器のお店を訪問します。
ここで注意したいのが、補聴器を購入する店舗の選び方。
補聴器購入で医療費控除を受けるためには、「認定補聴器専門店」および「認定補聴器技能者が在籍している販売店」がふさわしいとされています。メガネ店に併設されている補聴器ショップなどは、これに該当しない場合もあるので注意が必要です。
お近くの認定補聴器専門店を探す:認定補聴器専門店一覧
お近くの認定補聴器技能者を探す:認定補聴器技能者検索システム
上記店舗で、自分に合う補聴器を選定・試用したら、いよいよ補聴器を購入します。購入時には、販売店から領収書と「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しが発行されますので、大切に保管してください。
③確定申告時に医療費控除を申請する
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。補聴器を購入した年度には、自身で確定申告を行い、医療費控除の申請を行いましょう。
確定申告の際、税務署から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと領収書の提出を求められることがあります。また、申請後も、これらの書類は5年間保管する必要があります。
必要に応じて提出できるよう、あらかじめ準備・保管しておきましょう。
補聴器の医療費控除が適用される時期はいつ?還付金額はいくら?

通常、問題なく申請ができていれば、申請からおよそ1か月~1か月半前後で指定の口座に還付金が振り込まれます。
還付金額に関しては、補聴器購入費の全額が返ってくる訳ではなく、決められた計算式に基づいて算出された購入代金の一部が還付されます。
実際の還付金額に関しては、本人の収入やその年の医療費の総額によっても大きく変わってきます。
「医療費控除 シミュレーション」などのキーワードで検索すると、計算ツールが多数公開されています。金額が気になる方はこのようなシュミレーションサイトなどで算出してみるのが良いでしょう。
まとめ
①補聴器相談医を受診する↓
②補聴器相談医からの書類を持参して補聴器販売店に行く
↓
③確定申告時に医療費控除を申請する
↓
④申請からおよそ1か月~1か月半前後で指定の口座に還付
※2024年6月時点の制度について説明しています。
難聴が軽度でコスパ重視なら!シャープの「メディカルリスニングプラグ」がおすすめ

補聴器購入は数十万円以上するものがほとんどですから、医療費控除が活用できるといいですね。
しかし、確定申告をする手間もそれなりにかかりますし、そもそもすでに所得税や住民税が非課税なので、医療費控除は自身にはあまり関係がない、という方もいらっしゃると思います。
もっと手の出しやすいお手ごろ価格の補聴器があったなら・・試してみたいと思いませんか?
シャープの補聴器「メディカルリスニングプラグ」は、99,800円(非課税)ととってもお手頃な価格帯でありながら、品質や安全性、有効性において高い基準をクリアした管理医療機器。細かい調整はオンラインで完結するので、忙しい方や外出が困難な方にもおすすめです。
調整や相談の対応はもちろん認定補聴器技能者をはじめとする「補聴器の専門家」。
安心と高コスパの両方を叶えるメディカルリスニングプラグ、みなさんもぜひ試してみては?
こちらから試すことができます。
補聴器をご購入される前には耳鼻咽喉科での受診をおすすめします。
≪この記事の監修者≫

田中智子
認定補聴器技能者
うぐいすヘルスケア株式会社・うぐいす補聴器 代表取締役
MBA(経営学修士)
補聴器を「日常生活をポジティブに自分らしく過ごせるようになるためのツール」と捉え、補聴器専門店「うぐいす補聴器」を開業。以前は有名補聴器メーカーのマーケティング部に所属し、全国5000店舗へ補聴器販売の指導を実施した経歴を持つ。高齢者難聴を得意とし、地域住民への啓蒙活動、高齢者への補聴器の装用トレーニングなども実施している。